その接客がクレームを作り出すbusiness psychology
クレームが悪化・モンスター化するお客様対応とは?! クレーム対応と接遇 お客様の心理
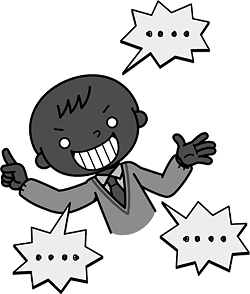
近年「モンスターペアレント」などいう言葉を耳にするようになりましたが、教育現場以外にも、日頃お客様等からのクレーム対応に頭を悩ませる企業のご担当者も多い事と思われます。
クレームがモンスター化するケースは、「クレーマー」と呼ばれように、その人の性格・パーソナリティーが原因となることもありますが、実は企業さんや対応をする側にもクレームを肥大・モンスター化させてしまう原因がある場合があります。
クレーマーの心理
例えば、業務の効率化を進めていて、担当部署が細分化されている企業さんなど、
以下のようなケースに、クレームが肥大・モンスター化する危険性があります。
⇒お客様が商品を使ったりして、不具合や不明な点が発生する (ストレスレベル1)
⇒問合せの電話をかける
⇒自動音声によって担当部署に繋がるように誘導される
⇒コール音が鳴る
⇒「ただいま電話が大変混みあっておりますのでしばらくお待ちください」 (ストレスレベル2)
※ここでの待ち時間が長ければ長い程、クレームはモンスター化する危険性が高まります
⇒繋がる
⇒担当者 「その件につきましては担当が異なっておりますため、別の部署をご案内しますのでおかけ直しいただけますでしょうか」 (ストレスレベル3)
⇒かけ直す (ストレスレベル4)
⇒「ただいま電話が大変混みあっておりますのでしばらくお待ちください」 (ストレスレベル5)
・・・
クレームというのは心理学的にはお客様がストレスを感じた時に発生します。
このケースでは、製品の不具合を感じた段階で、お客様はストレスを感じている訳ですが、ストレスを感じている所に、電話操作の手間、待ち時間というストレスが次々と重なっていきます。
そしてようやく電話が繋がったと思ったら、「担当が異なるのでかけ直してください」 との回答でストレスレベルはますます高くなります。
夫婦や恋人間などでも、小さな不満がある段階で相手の話を聞き解消していれば大きなもめごとにはなりませんが、我慢に我慢が重なりストレスが蓄積されると爆発がおきます。
上記のケースでは、問合せをするプロセスの中で、お客様の不満・クレームを成長?!させてしまっているのです。
当然、不満・ストレスレベルが一定量を超えればお客様は爆発します。
(最後にクレームの受け皿となった担当者は大変な思いをする訳です;;)
業務の効率化、細分化をすすめると、このような電話応対の仕組みはやむを得ない部分もあるかと思いますが、
クレームの肥大・モンスター化を防ぐために大切なことは、お客様の不満が成長する前に、できるだけ小さな段階で解消しておくことが大切です。
心理学・カウンセリング技術を活用した接遇・クレーム対応研修
悪質クレーマーの心理がわかれば怖くない!(公開セミナー開催しております)
日本心理教育コンサルティング
クレーム対応に役立つ おすすめ講座・各種情報
- クレーム対応 怒りを静める心理学
- 電話でのクレーム対応の時注意するべき点は?!
- クレーム対応に活用できる! プロのカウンセラーに学ぶ 聞く技術 傾聴力開発講座
- クレーム担当者のメンタルヘルス対策 メンタルヘルス研修
- 怒りのセルフコントロール アンガーマネジメントセミナー
- 言いづらいことを上手に伝える方法 アサーショントレーニング
- 上手な話し方・聞き方を身につける コミュニケーショントレーニング
- 心理学の基礎を学ぶ 対人心理学基礎研修
- お客様の心理を学ぶ ビジネス心理学
- 心を鍛える方法
- あなたは心配性?
⇒SITE INFORMATION
・集中力開発
・イメージトレーニング
・キャリアカウンセリング
※クレームを招きやすい一言
「私は担当ではないので・・・」
「おかけ直しいただいてもよろしいですか」
